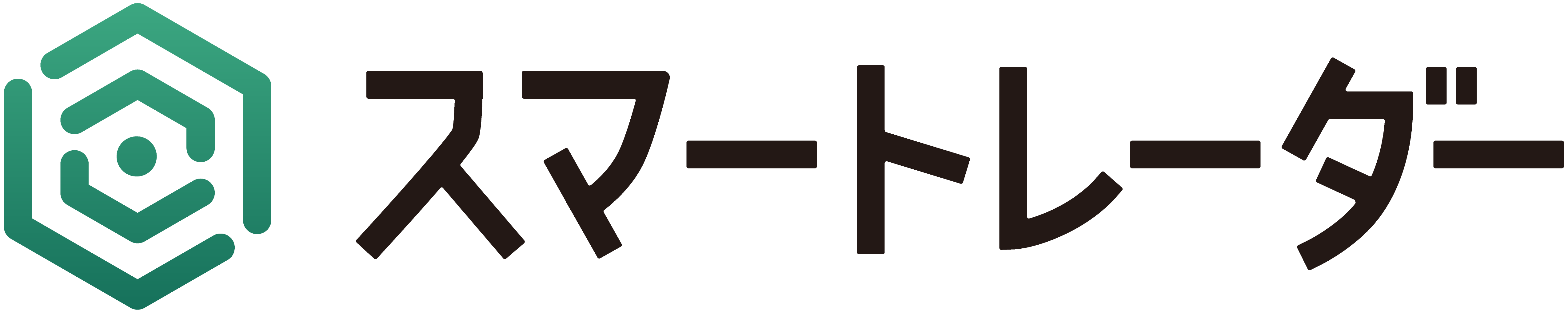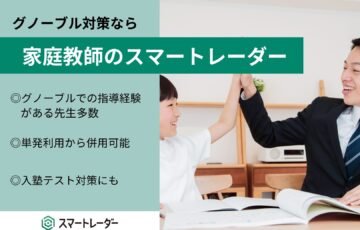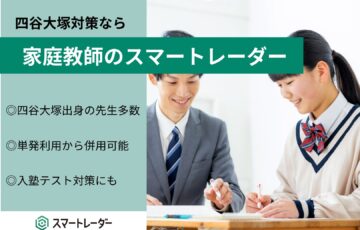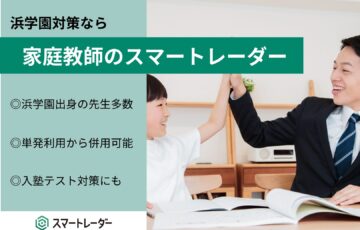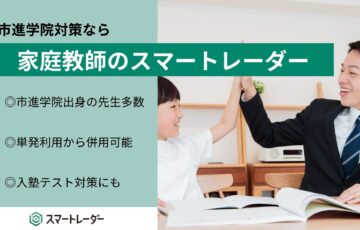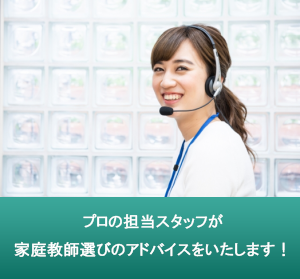四谷大塚は関東に多くの校舎を持つ老舗の塾です。入塾テストや授業はレベルが高く、「入塾テストで合格するにはどうすればいいの?」とお悩みのご家庭も多いのではないでしょうか。
この記事では、四谷大塚の入塾テストの難易度や合格基準、落ちる子の特徴、落ちた場合の対応策まで、気になる情報を網羅的に解説します。
Contents
四谷大塚の入塾テストとは?
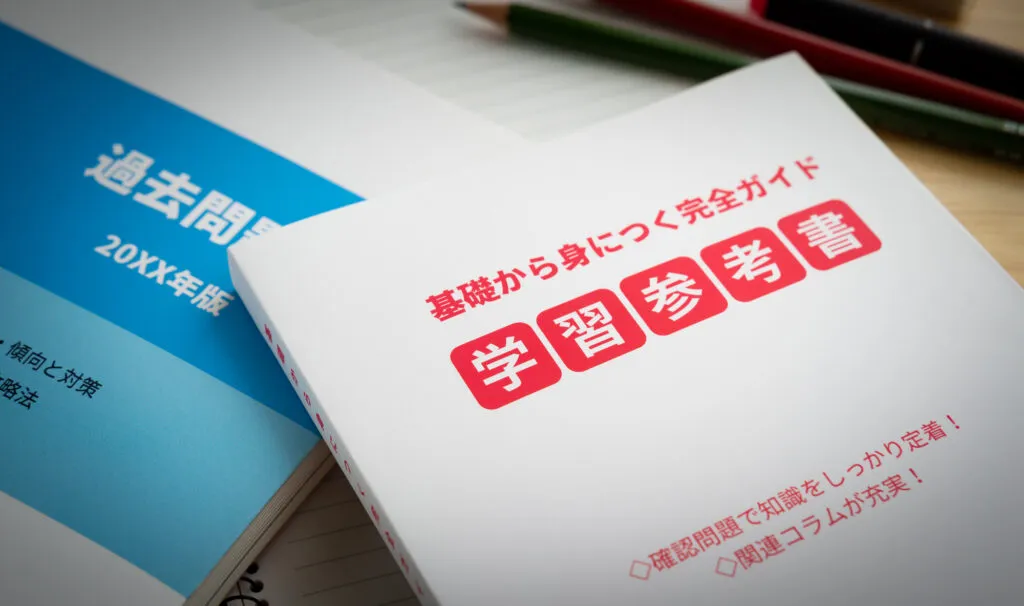
テストの目的と概要
四谷大塚の入塾テストは、学力別クラス編成や、受験準備に必要な基礎力の有無を確認するために実施されるテストです。
このテストの結果をもとに、中学受験に向けた教材「予習シリーズ」の学習を、その子に合ったレベルから無理なく始められるようにするのが目的です。
入塾後のクラス替えの仕組みについては、以下の記事で詳しく解説しているのであわせてご覧ください。
四谷大塚の組み分けテストの仕組み、次回日程、出題範囲と対策方法について紹介
受験対象の学年と時期
入塾テストは小学1年生〜6年生を対象に、年間を通じて複数回実施されています。
特に新年度に向けた1〜2月の受験者数が多く、競争率も高めです。
入塾テストの難易度や合格ラインは?
入塾テストの難易度は?
四谷大塚の入塾テストは大手中学受験塾の中でトップレベルに難しく、SAPIXよりも難しいと言われています。問題用紙が回収されるため、出題傾向の分析が難しく、情報が少ないことも難しいとされる原因です。
入塾テストの合格率は?落ちたらもう無理?
四谷大塚の入塾テストの合格率はおよそ50%ほどと言われています。半数が不合格になるため、落ちたという内容のブログも多く見られ、不安に感じる方も少なくないでしょう。
しかし、四谷大塚の入塾テストは何度でも受け直すことができるため、半分は不合格と割り切って何度もチャレンジすることをおすすめします。
また、四谷大塚では入塾テストに不合格になった子に学習指導をしてくれます。中学受験を志すなら早いタイミングでとりあえず入塾テストを受けておくとよいでしょう。
合格基準点は?
およそ5~6割の点、偏差値にして50前後が取れれば合格できると言われています。四谷大塚の入塾テストは時間が足りないとよく言われるため、取れる問題を確実に解いて、難しいところはきっぱり諦めるというテクニックも必要になってきます。
入塾テスト以外の入塾の方法はある?

実は入塾テストを受ける以外に四谷大塚に入塾できる方法が2つあります。
全国統一小学生テストを活用する
全国統一小学生テストでおよそ偏差値50程度を獲得すると、入塾資格審査合格証が届くと言われています。これを取得すると入塾テストに合格したものとみなされ、入塾テストを受けずに入塾することができます。
体験授業の週テストに合格する
もう一つの方法は体験授業を受けて週テストというものに合格することです。
しかし、四谷大塚のカリキュラムは進度が早いため、学校の学習だけでは対応することが難いことがあるため、事前の入念な対策が必要です。
四谷大塚の入塾テストを受けるまでの流れ
それではここからは具体的に四谷大塚の入塾テストを受けるまでの手順を解説します。
① 申し込みはWebフォームからスタート
まずは四谷大塚の公式サイトにある申し込みフォームから入塾テストのエントリーを行います。送信が完了すると、自動返信メールが届く仕組みになっており、申し込み内容の控えとして確認できます。
② 校舎からの連絡を待つ
申し込み後、校舎の担当者からメールまたは電話で連絡があります。
③ テスト当日は保護者向け説明会も実施
入塾テスト当日は、保護者の方を対象とした説明会も同時に行われます。
④ 結果連絡
試験の結果連絡は、後日受験した校舎からあります。
⑤ 校舎での個別面談で学習方針を確認
合格後は、校舎にて保護者との個別面談が行われます。お子さまの現在の学習状況や、今後の学習目標、どのようなサポートが必要かなどの話し合いができます。
⑥ コースの決定と入塾手続き
面談を経て、テスト結果に応じた最適なコースが提案され、受講クラスが決定します。その後、正式な入塾手続きへと進んでいきます。
入塾テストの問題内容と出題傾向は?
四谷大塚の入塾テストは、学年によって出題内容が大きく異なるため注意が必要です。
新小学3年生までは国語と算数の2科目、新小学4年生以降は国語・算数・理科・社会の4科目で実施されます。
今回は、全学年共通の国語と算数に絞って解説していきます。
国語の出題傾向
国語では、物語文や説明文といった長文読解問題が中心となっており、文章をしっかり読み解く読解力が求められます。
「国語が最後まで解き終わらなかった」という声も多く聞かれるように、文章量が多いため、読むスピードや集中力を求められるのが特徴です。
また、単なる選択問題だけでなく、自分の言葉で答える記述式の問題も一部含まれており、文章の要点をつかむ力や、表現力も試されます。
そして、語句の意味や使い方などを問う語彙力の確認も出題されるため、普段からの読書習慣が得点に大きく影響すると言えるでしょう。
算数の出題傾向
算数では、基本的な計算力に加え、文章題や図形問題などが幅広く出題されます。単なる計算だけではなく、条件を整理しながら考える力が求められるため、応用力が問われる問題が多いことが特徴です。
また、中には難関中学校の入試を意識したレベルの高い設問も含まれています。そのような問題では、内容を正しく理解するだけでなく、柔軟に考えを広げていく力が必要です。
そのため、答えを導くまでの道筋をじっくり考える思考力が求められます。
過去問はある?
残念ながら、公式の過去問集は一般には公開されていません。
ただし、「全国統一小学生テスト」の過去問や、予習シリーズ準拠の問題集が出題形式に近い内容となっています。
入塾テストに向けた短期間での学習方法
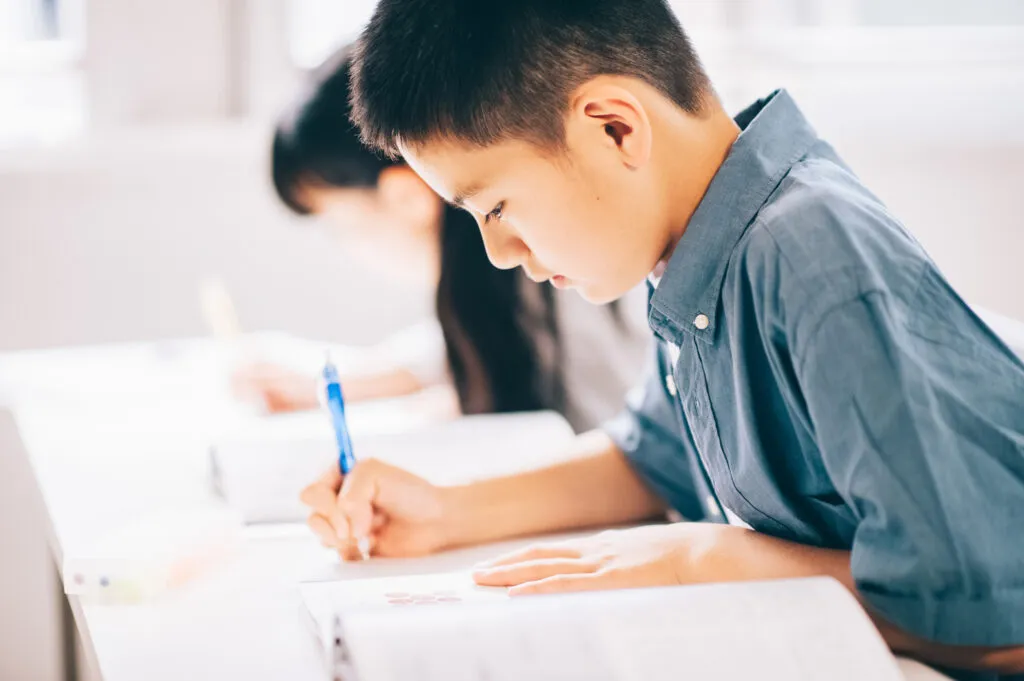
ここからは、入塾テストに向けて、短期間で成果を出すための学習方法を国語・算数、そして両科目共通の視点から紹介します。
短期間で成果を出すには?
国語の学習方法
国語の力を伸ばすには、テスト日までに、できるだけ多くの文章に触れておくことが効果的です。特に音読を取り入れることで、文章を正確に読み取る力が養われ、語彙力の向上にもつながります。
また、入塾テストでは記述問題も多いため、自分の言葉で考えをまとめる練習をに取り入れてみましょう。加えて、漢字練習では「とめ・はね・はらい」などの細かな部分まで意識することで、丁寧に書く癖を身につけることができます。
算数の学習方法
算数ではまず、基礎的な計算練習をテスト日まで毎日続けることが大前提です。さらに、入塾テストでは応用問題や思考型問題も出題されるため、図形や文章題にも積極的に取り組み、考える力を養うことが求められます。
また、計算や図を描く際は「丁寧かつ素早く書く」ことを意識することで、正確性とスピードの両方を高めることができます。
両科目共通の学習方法
どちらの科目でも、一度間違えた問題をそのままにせず「解き直し」を徹底することが非常に大切です。自分がどこでつまずいたのかを把握し、同じミスを繰り返さないようにすることで、学力は着実に伸びていきます。
おすすめ教材
日々の学習に取り入れたい教材として、まず四谷大塚のカリキュラムに沿った「予習シリーズ」があります。これは入塾後も使われる教材なので、事前に慣れておくとスムーズに学習が進みます。
基礎学力をしっかり固めたい場合には、公文式やZ会の教材もおすすめです。特にZ会は思考力を育てる問題が豊富で、応用問題にも対応しやすくなります。
また、市販されている「中学受験算数ドリル」なども、計算力や文章題のトレーニングに効果的で、家庭学習に取り入れやすい教材です。
落ちる子の特徴とは?

ここでは、実際に落ちる子の特徴について詳しく解説します。
日々の学習習慣が無い
毎日の学習が定着していない子は、問題の処理スピードや集中力、基礎知識の定着度が低い傾向にあります。
入塾テストでは時間内に多くの問題をこなす必要があるため、「勉強する習慣があるかどうか」が合否を分ける重要なポイントになります。
特に家庭学習の習慣が無い場合、四谷大塚のペースについていくことも難しくなるため、早い段階で学習のリズムを整えておくことが大切です。
学校のテストがいつも平均点以下
学校の定期テストや確認テストで平均点を下回ることが多い場合、基礎的な知識が不足している可能性があります。
四谷大塚の入塾テストは、学校よりもやや難易度が高い出題がされるため、基礎の理解が不十分だと太刀打ちできません。まずは、学校の学習内容をしっかり理解し、定着させることが重要です。
1つの問題に固執してしまう
テスト中に難しい問題に時間をかけすぎてしまい、他の問題を解く時間がなくなるというケースも見られます。
限られた時間の中で、取れる問題を確実に得点する「見極め力」や「割り切る力」も合格には欠かせません。解けない問題に固執せず、気持ちを切り替えて次に進む姿勢が求められます。
これらの特徴に当てはまる場合でも、日々の学習習慣を整えたり、問題演習を重ねることで改善は可能です。
まずは次に紹介する入塾テストの対策方法を実践し、しっかりと準備を重ねてテストに臨みましょう。
四谷大塚の入塾テストの対策方法は?

では実際に入塾テストをどう対策すればよいのかを紹介していきます。
体験授業を受ける
1週間で1つの単元を学び終える四谷大塚の学習スタイルを早めに体験しておくことはおすすめです。
徹底的な予習と授業、そして復習のサイクルを身につけておくことで自宅学習のくせをつけることも可能です。また、週テストを受けることで自分の理解度を知り、先生からの学習指導を受けることもできます。
早い段階で入塾テストを受ける
四谷大塚のカリキュラムはペースが速いため、タイミングが早いほど学校との進度に差がうまれません。なので3年生までにテストを受けることをおすすめします。
入塾が遅れると塾の授業のキャッチアップも難しくなっていきます。
四谷大塚の問題集を使う
四谷大塚の問題集を使って対策するのも効果的です。この問題集の基礎的なところが解けていれば、入塾テストに合格することも十分に可能です。
学年に応じて「はなまるリトル」や「予習シリーズ」などの問題を使って対策しましょう。
家庭教師を使う
とは言っても、ご家庭でしっかりとした対策を行うのは保護者の方にとって難しいでしょう。その場合は四谷大塚の入塾テストに精通した家庭教師の活用をおすすめします。
こうした家庭教師であれば、お子さまの現在の学習状況を丁寧に把握したうえで、本番に向けた最適な学習プランを提案・指導することが可能です。
中でもおすすめなのが、家庭教師マッチングサービス「スマートレーダー」です。スマートレーダーには、四谷大塚出身の先生も多数在籍しています。
四谷大塚の難易度の高い問題への対策や入塾テスト本番に向けた準備も家庭教師の先生にお任せいただけます。ぜひ一度スマートレーダーをご検討ください。
どうしても落ちてしまう場合の対策法とは?

四谷大塚の入塾テストに何度か挑戦しても、なかなか合格できないというような場合は、どう対応すればよいのでしょうか?
ここでは、不合格が続いた場合に取るべき対策をいくつかご紹介します。
校舎に直接アドバイスを求めてみる
まずは、受験した校舎に連絡を取り、「どうしても入塾したいのですが、どのような対策をすればよいでしょうか?」と素直に相談してみましょう。
塾側は、お子さまの現状を踏まえたうえで、実力不足の原因や優先的に取り組むべき単元、使用すべき問題集などについて丁寧にアドバイスをくれるはずです。また、学習習慣をどのように身につけるべきかといった具体的な相談にも乗ってくれるでしょう。
子どもの自信を守るフォローも忘れずに
何度も不合格が続くと、お子さまが「自分はダメなんだ」と感じてしまうこともあります。しかし、四谷大塚の入塾テストは合格率約50%で、半数は不合格になる試験です。
過去には、不合格を経験しながらも挑戦を続け、最終的に合格して力を伸ばした子も多くいます。結果を見るのではなく、努力している姿に対して前向きな声かけを心がけましょう。
お子さまが自信を失わず努力を続けられるよう、保護者のフォローが大切です。
四谷大塚に詳しい家庭教師にサポートを依頼する
中学受験においては、塾と家庭教師を併用するケースも少なくありません。特に、四谷大塚のカリキュラムや入塾テストに詳しい家庭教師に短期間でも指導を受けることで、出題傾向に合わせた対策ができ、効率的な学習につながります。
スマートレーダーなら四谷大塚出身の先生も多数在籍しています。四谷大塚に詳しい家庭教師の先生に依頼してみませんか。
2025年度入試<関東>の注目校の塾別合格実績
| 学校名 | 種別 | 定員 | 関東の主要塾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPIX | 早稲田 アカデミー |
四谷大塚 | 日能研 | 栄光 ゼミナール |
|||
| 開成 | 私立 | 300 | 98 | 40 | 75 | 45 | 50 |
| 麻布 | 私立 | 300 | 115 | 52 | 80 | 50 | 60 |
| 聖光学院 | 私立 | 225 | 135 | 63 | 90 | 60 | 70 |
| 海城 | 私立 | 290 | 100 | 40 | 60 | 50 | 55 |
| 桜蔭 | 私立 | 235 | 125 | 50 | 80 | 55 | 65 |
| 女子学院 | 私立 | 240 | 140 | 60 | 90 | 65 | 75 |
| 豊島岡女子学園 | 私立 | 160 | 130 | 50 | 85 | 60 | 70 |
| 渋谷教育学園幕張 | 私立 | 295 | 102 | 45 | 110 | 50 | 90 |
| 渋谷教育学園渋谷 | 私立 | 175 | 95 | 35 | 80 | 50 | 60 |
| 広尾学園 | 私立 | 240 | 120 | 40 | 85 | 55 | 65 |
| 筑波大学附属駒場 | 国立 | 120 | 70 | 40 | 50 | 30 | 45 |
| 筑波大学附属 | 国立 | 80 | 80 | 50 | 60 | 45 | 55 |
| 小石川中等教育学校 | 都立 | 160 | 60 | 45 | 50 | 30 | 40 |
| 合計 | 1775 | 670 | 1000 | 580 | 715 | ||
まとめ
今回は四谷大塚の入塾テストについて、難易度や合格基準、落ちる子の特徴、落ちた場合の対応策まで解説しました。
四谷大塚の入塾テストは、難易度が非常に高く、全国でもトップレベルと言われています。そのため、事前の対策は欠かせません。
そうした対策をお考えの際は、家庭教師マッチングサービス「スマートレーダー」の活用をご検討されてはいかがでしょうか。